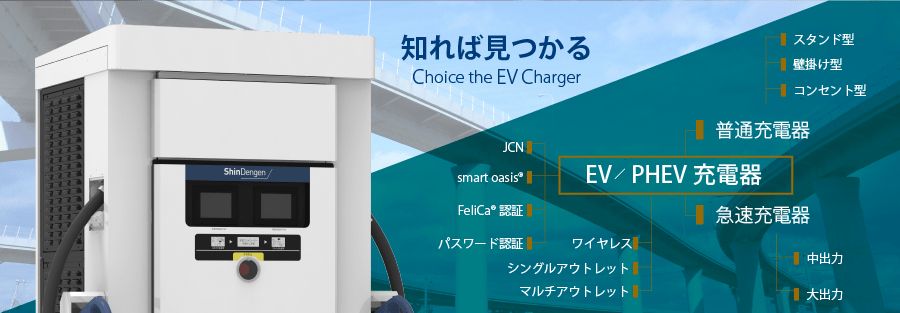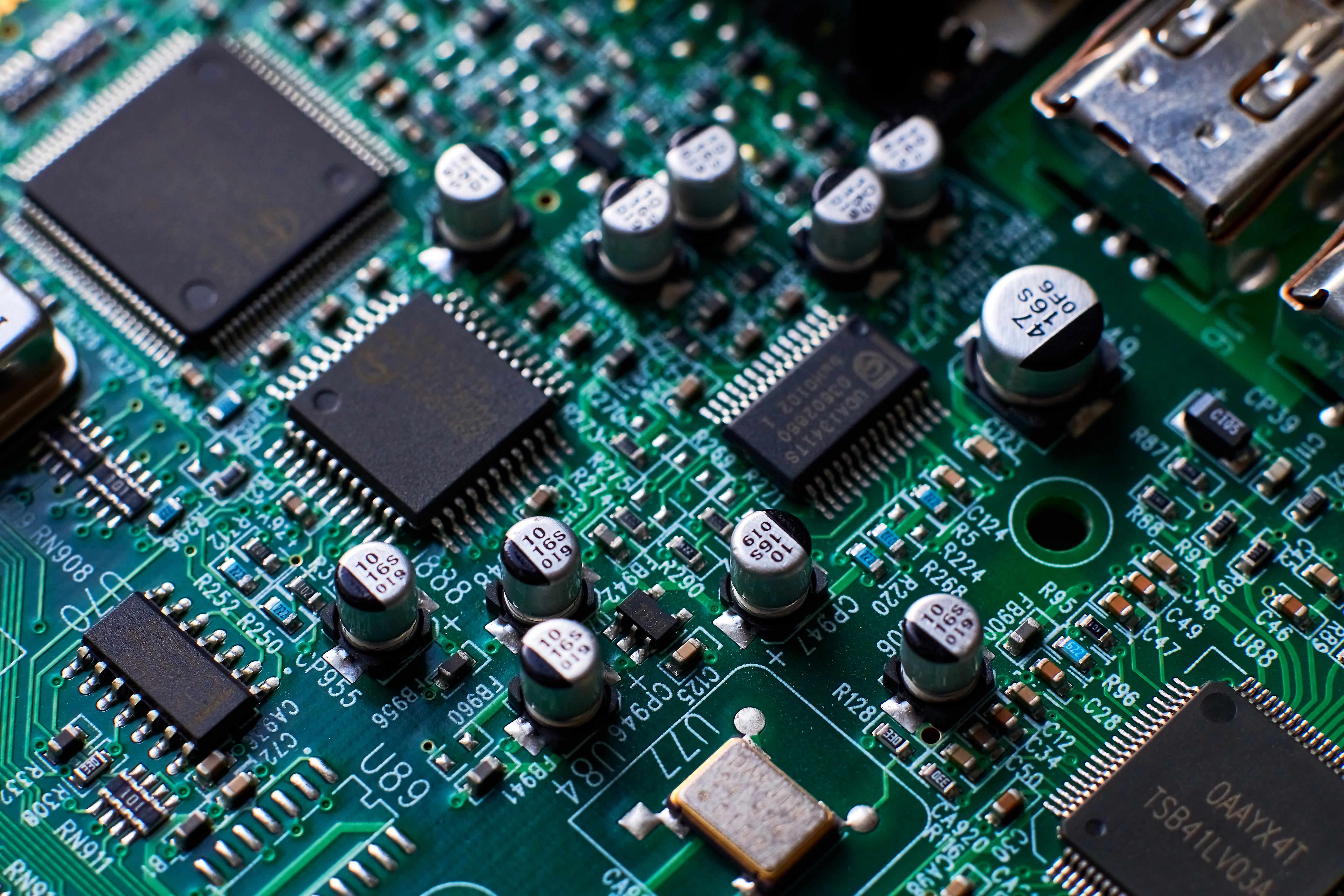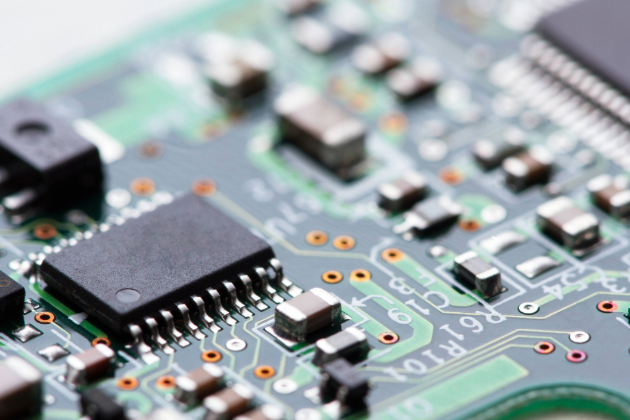EVトラック導入のメリット|将来の普及の課題についても解説
燃料費高騰・環境規制強化といった諸問題の解決に向けて、国家だけでなく企業単位でも対策が求められる中、自動車業界はEV化を進めるべく取り組みを進めています。このような流れは、運送業など車両を利用したビジネスを展開する業種の企業にとっても他人事ではなく、近い将来にはトラックのEV化も現実味を帯びてきています。この記事では、EVトラックの普及が企業にもたらすメリットや、導入にあたってのハードルについて解説します。
【目次】
1.EVトラックの特徴
EVトラックとは、エンジンではなく「電気モータ」で駆動するトラックのことをいいます。主な動力源はバッテリの電力で、エンジンを搭載するトラックと違い、走行中に二酸化炭素・有害排出物を排出しないのが特徴となっています。
モータを使用しているトラックであることから、エンジン車で走行する場合と違い、変速の際にギアを変える必要がなく、アクセルを踏むだけでスムーズな加速ができます。この点は、ドライバーの作業負担を軽減するポイントになるでしょう。
勤務時のメリットとしては、走行時や停車時の騒音を抑えられる点があげられ、夕方や夜間の配達になってしまった場合も騒音問題などに発展するリスクが少ないでしょう。そのため、都市部での配送・短距離配送などでは、徐々にEVトラックの導入・運用の動きが進められています。
2.EVトラックを導入するメリット
自社で新たにEVトラックを導入するメリットとしては、次のようなものが考えられます。
二酸化炭素排出量の削減
物流業界を含め、すべての業界における課題の一つに「事業運営により生じる二酸化炭素の排出量を削減する」ことがあげられます。世界各国でガソリン車・ディーゼル車の新規販売禁止の動きが強まれば、新たにガソリン車・ディーゼル車のトラックを確保することそのものが、非常に難易度が高い選択肢になるものと考えられます。
逆に、自社でEVトラックへのシフトが成功すれば、事業にもたらす影響を最小限に抑えることが可能になります。また、環境規制への対応が進んでいる企業として、取引先やESG投資家などに評価されやすくなることも予想されます。結果として、自社の経営にポジティブな影響をもたらすことが期待できます。
業務負担・整備コストの削減
ギアチェンジを必要としないEVトラックは、運転手が変速操作を行う手間を省けるため、その分運転時の業務負担が軽くなるものと期待されています。エンジン車に比べて部品数が少ないのもEVトラックの特徴で、例えば定期的なオイル交換の必要性がなく、冷却・排気の仕組みも備わっていないため、それだけ部品交換の手間や整備コストを抑えられます。
回生ブレーキを搭載している車種なら、減速時にモータを発電に利用できるだけでなく、ブレーキパッド交換の頻度を減らすことにもつながります。オートマチック車の運転手が多い若い世代に仕事を任せたい、運用中のトラックに発生する整備コストが馬鹿にならないと考えている企業にとって、EVトラックはメリットの大きい車種の一つです。
補助金・助成金が交付される場合がある
貨物自動車の運送事業者等は、商用車の電動化促進事業の対象となり、具体的には次のような車種が対象です。
●BEV(電気自動車)
●PHEV(プラグインハイブリッド車)
●FCV(燃料電池自動車)
トラックの補助率は「標準的燃費水準車両との差額の2/3等」となっており、充電設備に関しても「1/2等」の補助率が適用される場合があります。また、公益社団法人 全日本トラック協会においても「環境対応車導入促進助成事業」が実施されています。令和6年度の場合、所定の条件を満たした電気自動車につき、30万円の助成金が交付されます。
3.EVトラックが将来普及するにあたっての課題
EVトラックが、将来日本で普及するにあたっては、次のような課題を克服する必要があるとされています。
ガソリン車に比べて長距離輸送が厳しい
トラックは長距離を移動することが多く、その分航続距離が長いため、現在各メーカーがラインナップしているEVトラックの航続距離では実用に堪えないと判断する企業は少なくありません。理論上、EVトラックが航続距離を長くするためには、それだけバッテリの大容量化が必要になるため、積載能力や電費の関係から大容量化に踏み切れないという一面があるのです。
ガソリン車と同等の時間での充電が難しい
ガソリンで動くトラックの給油時間は、長くても数分程度で終わるため、稼働時間に大きな影響はないものと考えられます。しかし、EVトラックは急速充電でも1時間以上の充電時間が予想され、その間ドライバーは運転することができず、結果的に収益が減少する恐れがあります。
導入時はトラック以外のコストも想定する必要がある
先述した通り、EVトラックは急速充電にも時間がかかるため、出発時はできるだけ充電満タンで走行をスタートしたいところです。そのためには、各営業所に普通充電器を設けるなど、EVトラック導入に加えて充電設備を充実させるためのコストも想定しなければならないでしょう。
4.EVトラック普及の鍵は「大出力急速充電器」
EVトラックの運行をスムーズに進めるためには、高速道路や幹線道路沿いの休憩スポットを増やすとともに、できるだけスムーズ・スピーディーに充電できる大出力の急速充電器も普及させる必要があるでしょう。新電元工業では、EVトラック実証実験に採用された経験を活かしつつ、充電性能を向上させた急速充電器のラインナップを充実させています。
5.まとめ
EVトラックは、電気モータで駆動し、走行中にCO2を排出しない環境に優しいトラックといえます。導入メリットも豊富で、二酸化炭素排出量の削減による環境規制への対応、部品点数の少なさによるメンテナンスコスト削減、燃料費の安さによるコスト削減などが主なメリットとしてあげられます。
しかし、実際に導入する際の課題も存在しており、航続距離の短さ、充電時間の長さ、導入コストの高さなどが、多くの企業にとってハードルとなっています。普及にあたっては、充電時間を短縮できる大出力急速充電器の更なる配備も求められるでしょう。