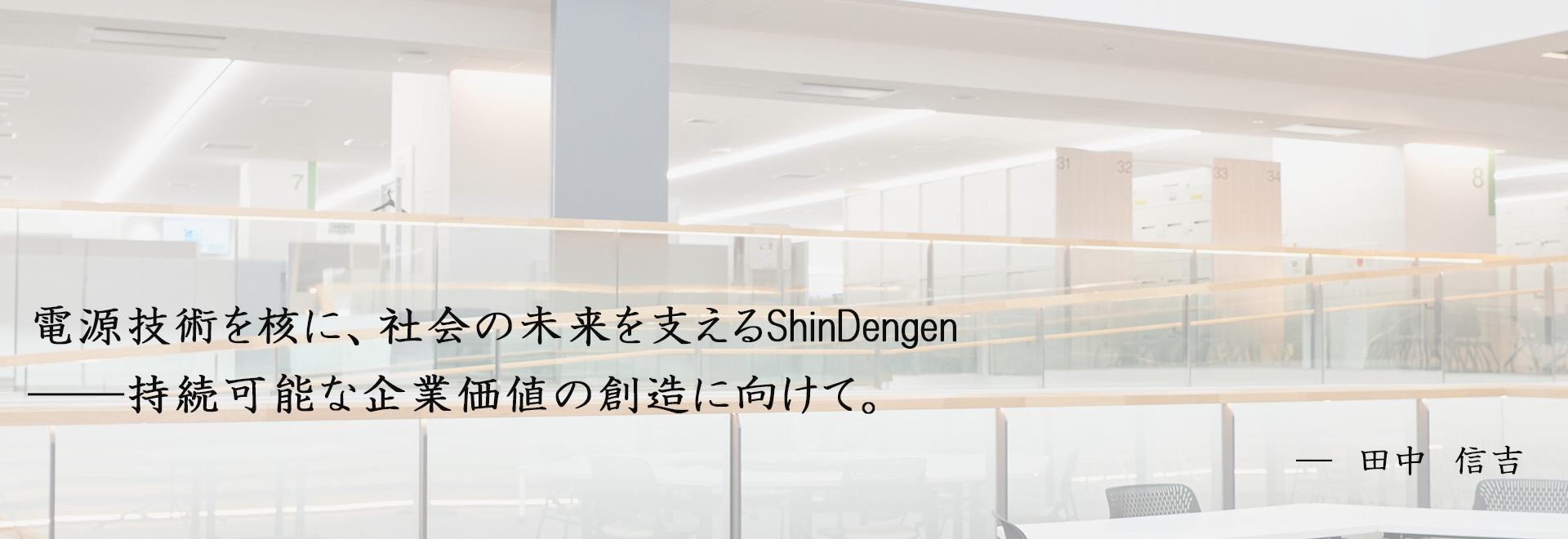トップインタビュー
Q1.創業から間もなく76年を迎える新電元工業ですが、その長い歩みの中で、時代が移り変わろうとも一貫して続けてきたことをお聞かせください。
当社をひと言で表すならば、「電源」という言葉こそが、その本質を最も端的に示す表現であります。「電源」から「ShinDengen」へ――社名には、創業以来一貫して電源技術を企業の中核と定め、絶えざる技術研鑽を重ねてきた当社の矜持と理念が込められております。
当社は、電源技術から派生した3つのコア技術を長年にわたり磨いてまいりました。すなわち、「半導体技術」「電源回路技術」、そして高品質な製品実現を支える「実装技術」であります。これらすべてを自社内で保有し、実用段階に至らせている企業は、業界内においても稀有な存在であると自負しております。この技術的基盤を礎に、現在は「パワーデバイス」「パワーユニット」「パワーシステム」の3事業を柱とし、「電源」を軸に据えた事業展開を推し進めております。各事業は独立して機能しつつも、共通の技術資産をもとに部門横断の連携を図り、相乗効果を通じて新たな製品や価値の創出へと結実させております。これこそが、当社のもう一つの大きな強みであります。
「電源」という言葉の本質に立ち返れば、そこには「無駄を生まないこと」が極めて重要な要素として内在しております。電源機器におけるロスは熱となって現れ、効率や耐久性に直結します。ゆえに当社は、損失の少ない高効率な半導体および回路設計の研鑽に尽力し続けてまいりました。これらの取組みは、電力の有効活用を通じて脱炭素社会の実現に資するものであり、SDGsにおけるマテリアリティとも深く呼応しております。
また当社は、自らを「パワーエレクトロニクスの会社」と明確に位置づけております。すべての事業領域――デバイス、電装品、通信用電源――がこの技術領域に立脚しており、近年の組織体制再編にあたっては各部門名称にも「パワー」を冠し、方向性の一体化を図りました。デバイス分野で例示するとすれば、当社は「パワー半導体」分野に特化し、経営資源を集中しております。市場環境は決して平坦ではありませんが、だからこそ、第17次中期経営計画において原点を見つめ直し、3つのコア技術を核とした経営を、より一層強固に推し進めてまいります。
Q2.2030年、あるいはそれ以降の将来を見据えた際に、新電元が目指すべき理想の姿とはいかなるものか。そして、その実現を支える「強み」や「戦略的資産」についてもお聞かせいただけますでしょうか。
少し長期的な視座に立てば、当社は現在、「長期ビジョン2030」の実現に向けた歩みを着実に進めております。このビジョンは、「新電元の革新的な技術を通じて、ステークホルダーから真に必要とされるパワーエレクトロニクスカンパニーとなる」ことを掲げており、今般始動した第17次中期経営計画は、その実現に向けた重要なマイルストーンと位置づけています。まずはこのビジョンの具現化を確実に果たし、その先に続く新たな成長ステージを切り拓いてまいります。
当社の根幹を成すのは、「3つのコア技術」と、それに基づく「3つの事業」です。これらは、単なる事業基盤にとどまらず、企業としての存在価値そのものであり、将来にわたり継続的に研ぎ澄まされるべき技術資産です。省エネ・省資源・脱炭素といった現代社会の喫緊の課題に対し、いかに貢献していくか。その鍵を握るのが、製品における「ロス」や「発熱」の低減であり、それによってお客様に対し、より高効率かつ低コストな電力活用の手段をご提供することが、当社の社会的使命と認識しております。個々の製品にとどまらず、システム全体を視野に入れたトータルな提案を通じ、より高度な課題解決に取組んでまいります。
技術革新の観点においては、「半導体」分野では素材選定や新素材の導入を通じた高性能化を、また「回路製品」では新たな回路方式の採用により、電力効率の最大化を追求しています。特に、パワーデバイスにおいては「エネルギーロスの最小化」、回路ユニットにおいては「電力変換効率の極限への挑戦」を技術的テーマと定め、日々研鑽を重ねております。こうした中核技術の高度化は主として研究開発の領域に属しますが、事業化には一定の時間を要します。ゆえに私たちは、研究から実用化までの「技術の橋渡し」を確実に遂行し、各プロセスを着実に積み上げてまいります。
Q3.第16次中期経営計画(2022年~2024年)を振り返り、掲げた戦略とその成果について、どのように総括されているかをお聞かせください。
当初掲げた目標は、売上高1,180億円、営業利益率6.6%、ROE8.3%というものでした。私自身、そのうち2年間、社長としてこの計画の遂行に尽力してまいりましたが、結果としては、中国経済の減速や地政学的リスクの顕在化といった外部環境の急変、特にデバイス事業への影響が甚大でありました。その結果、最終年度の実績は売上高1,058億円、営業利益1億2,800万円、営業利益率0.1%、ROEはマイナス3.6%と、目標とは大きくかけ離れた結果となり、残念ながら厳しい総括とならざるを得ません。この結果を真摯に受け止め、次の中期計画にしっかりと活かしてまいります。
セグメント別では、電装事業、とりわけ二輪車関連は堅調を維持しましたが、中国市場の失速や原材料高騰の影響により、デバイス事業の収益が大幅に悪化しました。この状況を踏まえ、2024年度には覚悟をもってデバイス事業の構造改革に着手。「生産・物流・販売」の各機能を抜本的に見直すとともに、350名規模の人員削減を断行し、2025年度には約15億円の利益改善を見込める体制を整備いたしました。市場環境を見極めながら、黒字化の実現を目指しております。
一方、ダイオード製品の開発においては、中国勢との競争が激化する中、小口径ウエハーの大口径化を推進。一定の成果が見えつつあり、コスト低減を通じた収益性向上が期待されます。加えてパワーMOSFETにおいても、モジュール製品を含めた開発を進め、世代交代を図ってまいりました。これにより二輪・四輪向けの需要に応える製品群が整いつつあり、技術水準も競合に肩を並べる域へと高まりつつあります。
ユニット製品では、前中計期間中にEV二輪向け「パワーコントロールユニット(PCU)」のインド生産・販売を開始。EV化は一時的に停滞しておりますが、中長期的には二輪においても確実に進展するとみており、本製品は将来の柱と位置づけております。また、EV化の緩慢な進行を背景に、エンジン車の需要も当面は維持されると見込まれ、特にASEANやインド市場における成長は継続すると判断しております。こうした環境を踏まえ、当社では2027年を目標にインド第2工場の設立を計画。既に用地を取得し、現在は導入設備や規模の検討を進めております。加えて、主要顧客である日系二輪車メーカーも現地での生産能力を大幅に増強する計画が報じられており、当社としてもこれに呼応すべく、供給体制を着実に構築し、確かな貢献を果たしてまいります。
―現在始動した第17次中期経営計画(2025年~2027年)における重点施策や主要な狙いについてもお聞かせ願います。
第17次中期経営計画に際しては、組織体制の大幅な見直しを断行いたしました。縦割り構造としての事業ユニット制(パワーデバイス、パワーユニット、パワーシステム)に加え、横断的な機能の強化を図るべく「ものづくりセンター」を新設し、工場間の共通課題への対応や原価低減の横展開を推進しております。併せて「技術開発センター」は全社の技術戦略を俯瞰し、各事業間のシナジー最大化に寄与する役割を担います。営業組織もユニット・デバイスの垣根を越え一元的に管理する体制とし、商機の逸失防止と提案力の強化を目指しております。
これまで断片化しがちであった「部分最適」を払拭し、「開発・生産・販売」を一体化した「全体最適」の視点に立つ経営体制の構築を志しております。体制としてはまだ不慣れな部分もありますが、必ずや成果を結ぶものと確信しております。さらに、EV化の遅延を踏まえ、事業ポートフォリオの見直しも実施いたしました。従来型製品であるダイオードやレギュレータは2030年においても一定需要が見込まれることから、引き続き基盤事業として位置付けております。その一方で、シリコンカーバイド(SiC)やパワーコントロールユニット(PCU)を次代の成長の柱として育成してまいります。
最後に、京セラ(株)からの事業買収について申し述べます。当社はチップ設計と供給に強みを持ち、この度、新たに京セラ(株)から取得するパワーデバイス事業は豊富なパッケージ技術を有しております。両社の強みを融合させ、多様な製品ラインナップの拡充と販路拡大を図る所存です。
Q4.持続的な成長の実現に向け、貴社が有する「強み」のさらなる深化や、マテリアリティを起点としたサステナビリティ経営の具体的な取組み、進捗状況についてご教示いただけますでしょうか。
当社の企業ミッションは、社会課題の解決と直結しており、日々その重みを実感しております。すなわち、当社の事業活動自体がサステナビリティ経営の実践であると自負しています。第17次中期経営計画の策定に際しては、マテリアリティ(重要課題)の見直しを行い、非財務KPIも現実に即して再定義し、具体的な目標を明確化いたしました。
環境面では、Scope1からScope3にわたる温室効果ガス排出量の検証を進め、その結果を踏まえたCO2削減目標を設定し、環境貢献の姿勢を社外に明示しております。また、人的資本の最大化を重要テーマと位置付け、人的資本経営の推進については既に情報発信を開始し、さらなる強化を図ってまいります。
技術革新を支えるのは「人財」であることを強く認識しており、計画の成否は人財の質にかかっております。ゆえに、採用強化を含む「人財戦略」の継続的推進に注力いたします。従業員間の「直接的なコミュニケーション」や「対話」、さらには「傾聴」の文化を尊重し、新たな発想やイノベーションの創出を促進する環境づくりにも努めております。教育面ではOJTを中核としつつ多様な研修プログラムを整備し、独自の「社内エンゲージメント指標」により従業員の仕事満足度を測定、迅速な改善を実現する体制も構築しました。加えて、フレックスタイム制度や在宅勤務の導入により、多様で柔軟な働き方を可能とし、一人ひとりの能力を最大限に発揮できる環境を整備しております。
これらの取組みを通じて、中長期的な成長と社会的価値の向上を追求し、「ステークホルダーから真に信頼され必要とされる企業」を目指して邁進いたします。何より「社内の調和」こそが企業の基盤であり、この調和の上に立ってこそ、真に社会に貢献できるものと確信しております。
Q5.株主・投資家をはじめとする多くのステークホルダーが、新電元の今後の飛躍に大きな期待を寄せております。そうした皆さまに向けた、メッセージをお願いいたします。
現在の経営環境は極めて不透明かつ厳しさを増しております。地政学的な緊張や、米国の政治動向をはじめとした変動要因が多く、先行きの予測は困難を極めます。そんな中、私は「目先の変動に過度に動じない」、すなわち“ジタバタしないこと”が必要であり、むしろ大切なのは、将来の成長に向けて今やるべきことを着実に積み重ねることにほかなりません。
当社が掲げる「長期ビジョン2030」で描いた理想像の実現に向けて、第17次中期経営計画はその重要な節目となるものです。既存製品のさらなる強化や、京セラ(株)からの事業買収による製品群の拡充、加えて次世代商材の開発・市場投入といった未来への布石を着実に打ってまいります。また、企業ミッションの実践を通じ、持続可能な社会の構築と企業価値の向上を両立させることこそ、私たちの揺るぎない使命と認識しております。
一方で、資本コストや株価を意識した経営において課題があることも認めざるを得ません。今後はこれらの課題に正面から向き合い、投資家の皆様の期待に応えることが不可欠です。その一環として、事業別バランスシートの導入や投下資本回転率等のKPI設定を進め、定量的かつ客観的な事業管理の強化を図ってまいります。資本効率を徹底的に追求することで、株主との対話を深め、市場からの信頼を一層高めていく所存です。
私の使命は、株主・投資家の皆様はもとより、お客様、地域社会、将来を担う若者、そして従業員に至るまで、すべてのステークホルダーから「信頼」と「誇り」を持たれる企業へと成長させることにあります。この志を胸に、第17次中期経営計画期間においても、全力で邁進してまいります。
本ページに記載されている内容は、2025年7月現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。