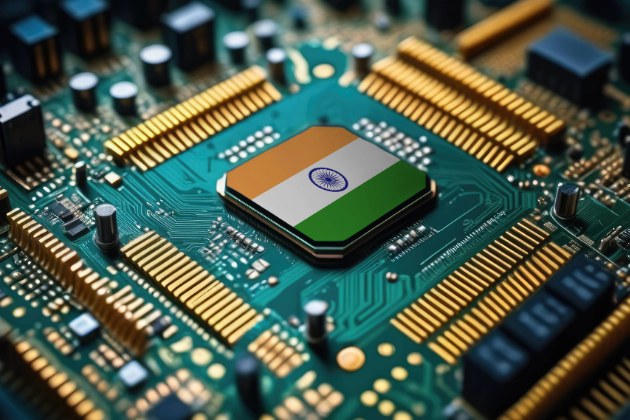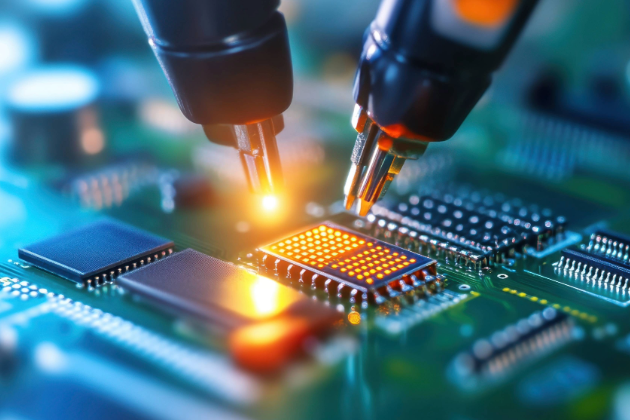V2Xとは|EVとの連携でできることや活用方法について解説
近年、通信技術によって自動車同士、または自動車とそれ以外のものを結びつける「V2X」という技術に注目が集まっています。V2Xは、特にEVとの連携促進が期待されており、効率的な移動や安全運転、レジャー・災害時の利便性向上などに役立つものと考えられています。その一方で、EVおよびV2Xの本格普及にあたっては、乗り越えなければならない課題もいくつか存在しています。この記事では、V2Xという技術について、EVとの連携や活用方法に触れつつ解説します。
【目次】
1.V2Xとその種類
V2Xとは、英語の「Vehicle to Everything」の略で、車両と様々なモノとの間で接続・連携を行う技術を指します。Everythingという単語が用いられていることからも分かる通り、V2Xに該当する技術は非常に多様です。以下、V2Xに該当する技術について、主なものをいくつかご紹介します。
V2V
V2Vは「Vehicle to Vehicle」の略で、車両同士の通信技術を指します。周囲を走行している車両と位置・速度情報を相互通信することで、安全な車間距離の確保や緊急車両の把握などができるようになり、事故や衝突のリスクを減らしつつ運転効率の向上が見込めます。また、事故防止の観点以外では、高速道路及び一般道路における渋滞緩和などのメリットも期待できます。
V2I
V2Iは「Vehicle to Infrastructure」の略で、車両と道路周辺のインフラ機器との間で通信を行う技術のことです。よく知られているものにETCが挙げられますが、信号機・道路標識・交通センサーといったインフラからも有益な情報が提供される仕組みが構築されると、信号の待ち時間・歩行者の位置・スムーズな運転ができる速度など、ドライバーが運転時に欲しい情報を取得しやすくなることが期待できます。
V2P
V2Pは「Vehicle to Pedestrian」の略で、車両・歩行者間の通信技術を指します。歩行者が持つ端末(スマートフォン・タブレットなど)と車両が連携することにより、歩行者の位置を伝達するイメージで考えると分かりやすいでしょう。運転上特に重要な機能としては、車両の死角にいる歩行者の早期検知が挙げられます。
その他
その他のV2Xとしては、車を端末と考えて制御ソフト・地図更新・エンターテイメントコンテンツ配信などを行う「V2N」や、アウトドア・災害時にEVから家電製品等へ電気を供給する「V2L」などが挙げられます。
2.V2XがEVユーザーにもたらすメリット
V2Xは、特にEVの効率的な運用に貢献する技術として知られています。以下、V2XがEVユーザーにもたらすメリットについて解説します。
省燃費(電費)化
EVは、ガソリン車の燃料補給に比べて充電時間が長くなる傾向にあります。そのため、目的地に移動するまで効率的に運転することの重要度は、どうしてもガソリン車よりも高くなります。V2Xによってエネルギー消費を最適化し、目的地までスムーズに着ける機能が備われば、ドライバーとしても安心して運転できるでしょう。例えば、EVに充電ステーションの位置が把握できるシステム・ソフトウェアが搭載されれば、最寄りの充電インフラまでの距離や位置関係、混雑具合などが分かるようになるため、充電待ち時間の短縮・電池切れリスクの低減が期待できます。
ドライバーのリスク・ストレス軽減
他の車両の接近を検知したり、死角から歩行者や自転車を発見したりできる機能が搭載されることで、ドライバーは事故リスクを大幅に軽減できるでしょう。加えて、渋滞解消やスムーズな移動が実現することで、運転中に無駄なストレスを抱えずに済むようになるものと考えられます。
EVの用途多様化
近年では、車中泊など車を移動・宿泊を兼ねて利用するユーザーが増えてきており、バッテリに多くの電気をストックしておけるEVの利用価値が高まっています。キャンプ場などでアウトドア用途に使用する場合は、EVの電力を使って家電を動かすことも可能になるでしょう。災害時は、EVを非常用電源として利用したり、電力ネットワークと連携したりするような使い方も想定できます。
3.V2XがEVに導入されるまでの課題
V2XがEVに本格導入されれば、自動車の運転環境は大幅に改善されるものと考えられます。しかし、V2Xを普及させるためには、次のような課題を解決する必要があります。
|
課題 |
詳細 |
|
V2Xに対応している車種のラインナップ増加 |
V2X機能が搭載された車両同士でなければ通信ができないなど、対応車種が増えなければV2Xのメリットを最大限享受するのが難しい |
|
通信規格の統一 |
V2Xの主流通信規格は以下2つに分かれている |
|
各種インフラ整備 |
インフラが十分に整備されていないと、使える地域が首都圏などに限定される恐れがある |
|
安定した通信環境の整備 |
車で移動中に通信障害が発生することで、重大な事故や大渋滞の発生につながらないよう、安定した通信環境の整備が必要になる |
|
セキュリティ対策 |
V2X導入車両に対するハッキングなど、車両制御に深刻なダメージが与えられないよう、セキュリティ体制を強化することが求められる |
4.V2XとEVの新たな可能性
V2Xシステムは、既存インフラの課題を解決する点において、様々な可能性を秘めています。新電元では、東京電力グループと協働で行った「電気自動車(EV)の放電機能を活用した機械式立体駐車場の稼働実証試験」を成功裏に完了しました。
この実証実験は、機械式立体駐車場が停電した際、車両出庫が困難になる点の解消を目的として行われましたが、実験ではEVから機械式立体駐車場への三相電力供給を実現し、停電時において駐車場の稼働・車両の出庫ができることを実証しています。 また、新電元では将来のEV本格普及を見据え、普通充電器・急速充電器をはじめとする環境・エネルギー製品を多数ラインナップしています。
その他、EVの電力変換を担う「降圧DC/DCコンバータ」のニーズにも、幅広く対応しています。
5.まとめ
V2X技術を搭載した車両が増えれば、ドライバーの負担が軽くなるだけでなく、歩行者の安全面での不安も軽減されるものと考えられます。EVに関しては、課題とされてきたエネルギー消費の最適化や使い道の多様化、充電にかかる時間負担の軽減なども期待できます。 また、アウトドア・災害時の電力供給源としても、EVは大いに活躍してくれることが予想されます。V2X搭載車両が普及するまでには、解決しなければならない問題も複数存在していますが、普及は決して遠い未来の話ではないでしょう。