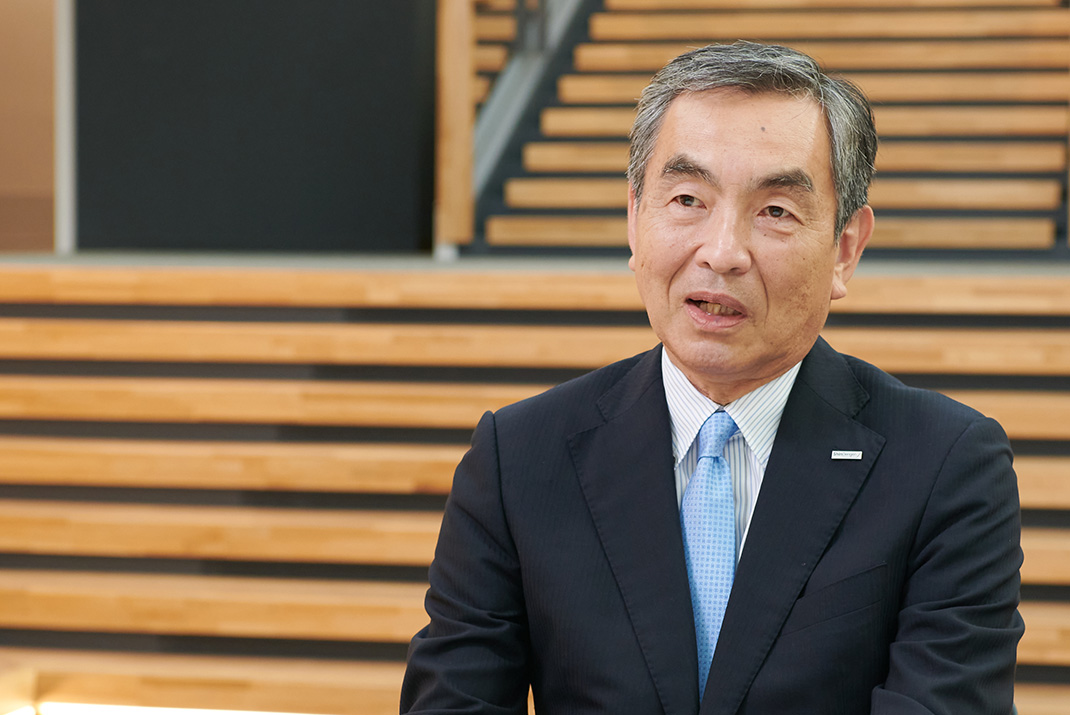Q1. 持続的成長を実現するうえで、新電元のコーポレートガバナンスの進化において特に重要とお考えのポイントを、現状との対比も交えてご教示ください。
西山社外取締役(以下、西山):今回は、昨年とは異なる視座から所見を述べさせていただきます。まず2024年度の業績を振り返ると、複数の要因が重なる中でも、「販売実績および見通しに関する情報把握の精度」に課題があったと認識しております。販売見通しの下方修正が利益減少に直結し、生産調整の遅れから在庫が過剰に積み上がる深刻な事態を招きました。これは取締役会の対応力のみならず、現場から経営層への情報伝達の仕組みにも不備があったことを示しており、情報連携と意思決定の精度向上が急務と痛感しております。この認識のもと、社長主導で「ものづくりセンター」が新設され、縦割り構造を超えた横断的機能の整備が始まりました。経営判断の質を高める基盤として期待されます。
また当社は2025年、京セラ(株)からの事業買収という転機を迎えます。新たに取得する事業の全社的統合とシナジー創出は経営の最重要課題であり、投資回収の観点からも早期成果が求められます。その実現には、組織運営とガバナンス体制の一層の強化が不可欠です。研究開発においても異なる企業文化を融合しながら前進する必要があり、統合そのものがガバナンスの力量を問う場面といえます。さらに、グローバル統制の観点では、工場に赴いて実際の生産現場を知ることで、当社のものづくりに対する理解を深めるとともに課題発掘の機会となりました。直近では、ベトナム工場を視察し、従来の成功に甘んじず、四輪シフトを見据えた新戦略の構築が必要であると実感しました。
最後に、取締役会の構成について申し上げます。現在は社外2名・社内4名で一定の独立性を確保しておりますが、独立取締役が過半を占める体制が求められる昨今の潮流を踏まえ、将来的な見直しも視野に入れております。人数構成のみならず、実質的な活性化に向けた議論を今後も深めてまいります。
北代社外取締役:(以下、北代):私からは「ステークホルダーとの対話の深化」の重要性について申し上げます。現在、当社が株式市場から評価を得ることができていない背景には、投資家との対話、すなわちIRの在り方に課題があると認識しています。中長期的な経営方針は一定程度発信されているものの、市場に説得力をもって伝わっていない――これが率直な所感です。この点において、今年度から社長室を設置し、IR活動の強化に着手されたことは極めて前向きな一歩であり、今後の進展に期待を寄せています。とりわけIRでは、戦略の意図や成果指標、M&A後のシナリオなどを定量的な根拠とともに示すことが、投資家の納得を得る上で不可欠と考えます。たとえば、京セラ(株)からの事業譲渡についても、「何を目的として取得したのか」「どのような価値を創出するのか」といった点を、よりストーリー性をもって明快に伝える余地があるのではないでしょうか。
併せて「グループガバナンスの再構築」も重要な課題です。当社はインド第二工場建設などグローバル生産体制の強化を進めていますが、地域ごとの事業環境に応じた統制の高度化が求められます。昨年のベトナム工場視察では現地での安定的運営を確認しましたが、インドでは異なる挑戦が待ち受けています。既存制度にとらわれず、柔軟な統治枠組みを構築していく必要があります。今後、海外拠点の拡充や新規事業の統合が進む中で、グループ全体の一体感をいかに醸成し、健全な統制を維持するかは、ガバナンス深化における重要な論点です。
Q2. これまでの取締役会における中長期的視点での議論を通じて明らかとなった、新電元が直面する課題についてお聞かせいただけますか。
西山:当社の最大の課題は、「成長の原動力となる事業をいかに見いだし、育てていくか」に尽きます。現在、旧・電装事業本部にあたるパワーユニット事業本部は安定的なキャッシュフローを生み、企業全体の財務を支える柱となっていますが、それを真に成長事業と呼ぶには、今まさに転機を迎えている段階と認識しております。一方、デバイス事業は2期連続の赤字が続いており、京セラ(株)からの事業譲受や構造改革につづく抜本的対応が急務です。「既存事業の再強化」と「新たな成長領域の探索」をいかに早期に確立できるかが、PBRやROEといった経営指標の改善に直結すると考えています。
また、「当社事業の競争力」の再認識も重要です。主力製品はコモディティ化の波にさらされ、特に中国勢との厳しい価格競争に直面しています。価格優位で勝つのは困難であり、技術による差別化こそが生き残りの道です。当社は「電力の高効率マネジメント」を中核に据え、EV、自動運転、生成AIなど次世代産業との親和性も高く、当社の技術的DNAが活かされる場面は必ずあると確信しております。
企業文化に目を転じれば、当社には慎重で安定志向の傾向が強く見られます。これは信頼構築の面で美点である一方、市場変化に応じた迅速な意思決定を妨げる面も否めません。制度による裏付けなくして文化は変わらない。意思決定のルールと責任を明確にし、企業体質を進化させる――社外取締役として、その制度設計に貢献してまいります。
最後に、役員報酬の削減や人員再配置といった構造改革の施策は、現場の強い危機感の現れと受け止めています。真の原因に向き合い、再発防止の仕組みを築くことこそ、私たちに課された責任です。「まだ、やるべきことがある」――それが今の私の偽らざる実感です。
北代:現時点の重要課題として、「スピード感ある意思決定と実行体制の確立」を挙げたいと考えます。「何を・いつ・誰が決めるのか」という判断の枠組みが曖昧であることが、組織の動きの鈍さにつながっているように感じます。
取締役会で議論すべき事項と、現場で迅速に決断すべき事項の線引きをより明確にすれば、全体のスピードは格段に上がるはずです。当社のような規模では、迅速かつ柔軟な判断こそが競争力の源泉であり、制度設計と運用の精度が重要です。
加えて、「ベンチマーク意識」の希薄さも課題です。他社との比較や業界内での立ち位置を定期的に検証することは、戦略の見直しに欠かせません。独自の強みを持つ一方で、外部との緊張関係が自社を客観視する機会となります。
社外取締役として、こうした視点を社内に持ち込み、対話を重ねることが私の役割だと考えています。
Q3. 実効性の高い取締役会の運営に向け、ご自身が特に注力されている事項についてご説明ください。
西山: 「実効性ある取締役会」の実現に向け、私が常に意識しているのは、「当社の常識が社会の常識とは限らない」との視点を持ち、社外からの問いかけと指摘を怠らないことです。善管注意義務の観点からも、重要な意思決定に際しては予定調和に流されず、自らの見解を明確に示すよう努めています。
昨年度は特に、営業現場の情報伝達に注目し、数値の前提やリスク対応、下振れ時の備えについて繰り返し問題提起しました。これは単なる結果評価ではなく、対応力を高める制度設計の課題と捉えています。
北代:社外取締役として「株主目線」での発言を心がけています。たとえばIRにおける開示のタイミングや内容の明瞭性については、「投資家なら何を知りたいか」という視点から問い直す姿勢を大切にしています。
また、社外取締役は社内情報へのアクセスに一定の限界もあるため、監査役との連携は重要です。監査役と社外取締役がそれぞれの視点から情報を共有し合うことで、よりバランスの取れた意思決定が可能となると考えております。年1回設けている懇談も取締役会の活性化に寄与しています。
Q4. ステークホルダーの皆様に向けてのメッセージをお願い申し上げます。
西山:当社は現在、既存事業を取り巻く厳しい経営環境の下、強い危機感をもって構造改革に全力で取り組んでいます。黒字化の早期実現は最優先課題であり、その覚悟をまずステークホルダー
の皆様にお伝えしたいと存じます。
一方、京セラ(株)からの事業譲受やインド市場への資本投資・経営参画は、既存事業の強化に資するものであり、当社の将来に大きな可能性をもたらすと確信しています。中長期的には技術開発を中核とする成長領域の育成に注力し、当該事業とのシナジーを活かしながら成果創出を目指します。
また、政策保有株式を活用した成長投資と株主還元のバランスも重要と考えており、中期経営計画で方針の透明化を進めるべきと考えています。インドや東南アジア諸国を軸としたグローバル展開の中で、皆様と共に未来を切り拓いてまいります。
北代:当社を取り巻く事業環境は極めて厳しく、社外取締役としての責任の重さを日々痛感しております。今後も「自らに何ができるか」「どうあるべきか」という問いを胸に、誠実に職務にあたってまいります。
当社には確かな技術力に加え、埼玉という地域に深く根ざし、地域社会から親しまれ、信頼されてきた歴史があります。こうした人的資本や社会関係資本といった“見えにくい資本”こそが、当社の価値の根幹をなすと確信しております。
株主の皆様をはじめ、全てのステークホルダーの皆様には、こうした多面的な価値をご理解いただき、引き続き温かいご支援を賜れましたら幸いです。
本ページに記載されている内容は、2025年7月現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。