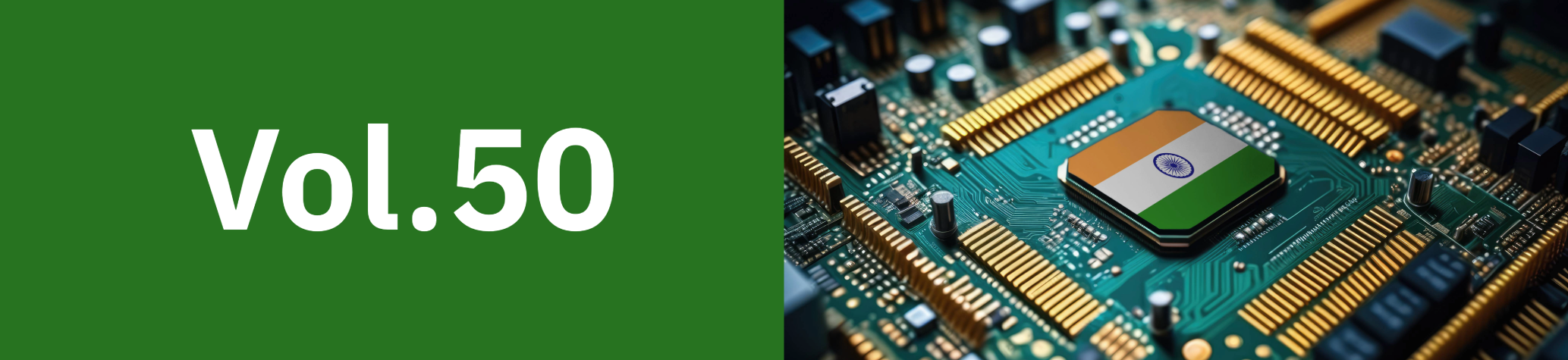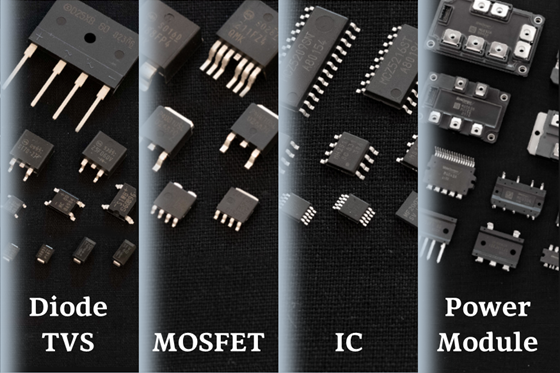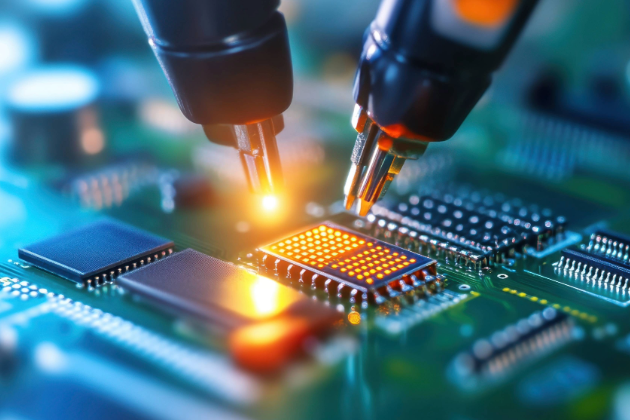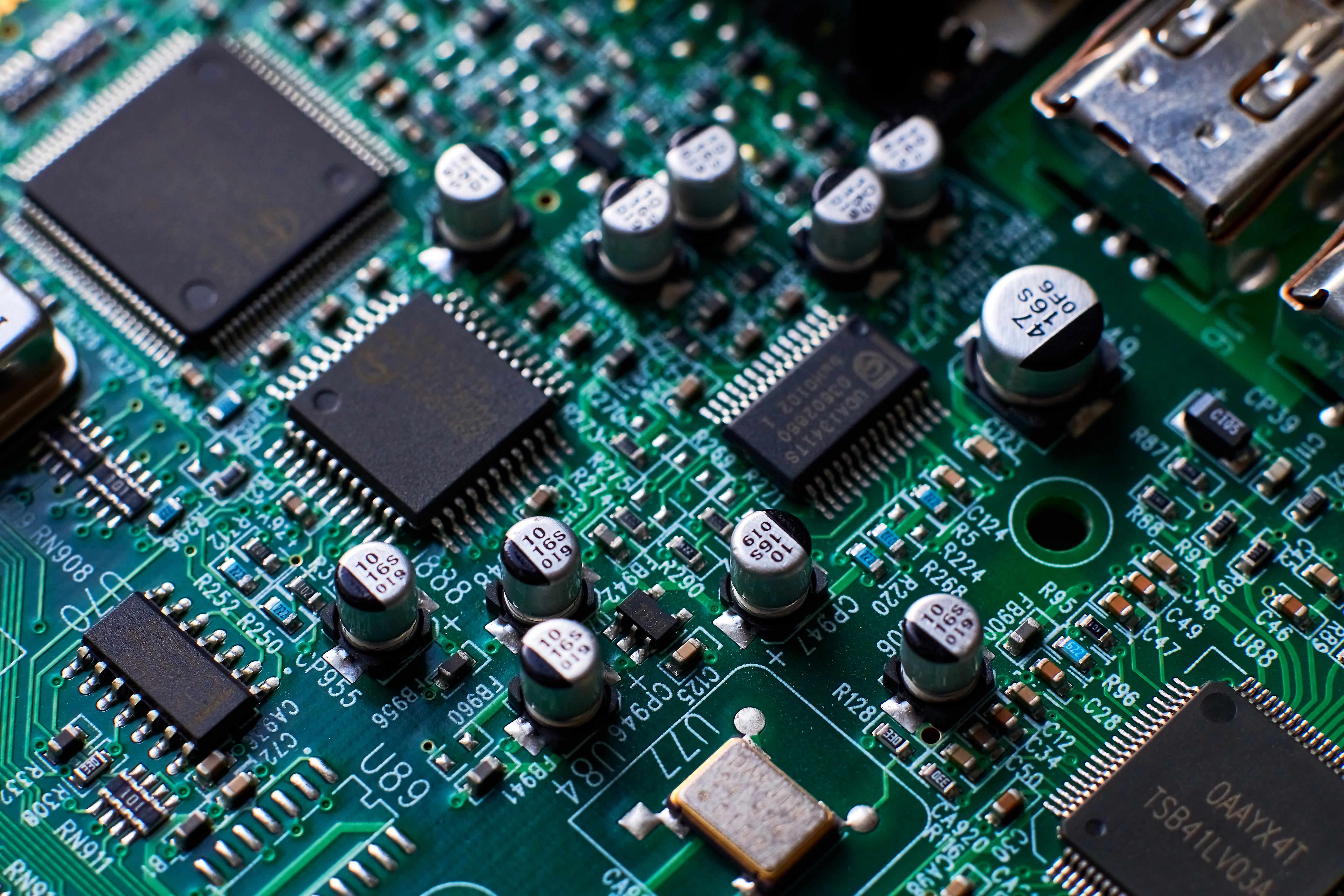インドが半導体の国産化を目指している理由|成功を分ける要素も解説
近年、インドではスマートフォン・自動車部品といった様々な産業の需要増加とともに、半導体市場が急速に伸びている状況です。その一方で、インド国内向けの集積回路や半導体デバイスは海外からの輸入に依存しており、インドはその状況から脱却するため「半導体の国産化」に向けて動きを加速させています。
しかし、インドが半導体の国産化を目指す理由は、決してそれだけではありません。この記事では、インドにおける半導体国産化のトレンドにある背景や成功を分ける要素、それに伴う各国の動きなどについて解説します。
【目次】
1.インドにおける半導体国産化の動き
インドが半導体産業の育成に本格的に乗り出したのは、シン政権下の2007年に「半導体工場の設立費用の一部を補助する政策」を発表した頃までさかのぼります。その後、2011年にはGDPに占める製造業比率を高め、雇用を創出する目的で「NMP(国家製造政策)」が打ち出されるなど、徐々に製造業振興の流れが高まってきました。
モディ政権下での主な取り組み2014年に発足したモディ政権では、国内製造業の強化を重要政策の一つに掲げ、以下のようなキャンペーンや政策を次々と打ち出しています。
Make in India(2014年)
製造業の振興を目的とした国家的キャンペーンで、投資・イノベーションの促進だけでなく、スキル開発や知的財産の保護など多方面の施策を含むものです。2024年現在も継続されており、インド政府が海外企業の投資を呼び込みながら国内生産を拡大するための“最重要プログラム”と位置づけられています。
Digital India(2014年)
インド国内の経済・社会のデジタル化を進めるための施策で、電子政府サービスの拡充やITインフラ整備などを主眼に置いています。通信ネットワークの高度化やデータ活用の推進を通じて、半導体を含む電子機器産業の需要拡大が期待されました。
NPE2019(国家電子産業政策2019年)
国内の電子産業全般を強化するための政策で、半導体をはじめとする電子部品の国産化促進や、輸出拡大に向けた生産体制の整備などが掲げられています。NPE2019の下で、一連の補助金・優遇スキームが具体的に実施されるようになりました。
各種スキームの導入(2020年)
- PLIスキーム(生産連動型優遇スキーム)
売上の増加額に応じて補助金を給付するもので、国内での生産拡大を促す狙いがあります。 - SPECS(電子部品・半導体製造促進政策)
電子機器の生産に必要な設備投資に対して補助金を給付するなど、半導体分野への投資を直接的に後押ししています。 - EMC2.0(電子機器製造クラスター計画)
製造拠点を集積してエコシステムを形成することで、半導体を含む電子部品の産業集積を図ります。
半導体・ディスプレイ工場新設への補助金制度(2021年)
新設工場に対して最大50%の補助金を支給するなど、大規模な投資を伴う半導体ファブ誘致のための施策が充実しました。
セミコンインディア(2022年)
半導体産業振興を目的とした大型イベントで、国内外の企業や投資家を集めて事業機会を提案・議論する場となっています。モディ政権が力を入れる“半導体の国産化”戦略をアピールし、海外からの直接投資を積極的に呼び込む狙いがあります。
国際的な連携強化(2023年)
さらに、2023年にはアメリカ・日本・EUなどとの間で相次いで協力の枠組みや覚書が結ばれました。たとえば米印共同声明や日印半導体サプライチェーンパートナーシップなど、半導体分野の国際的なサプライチェーン構築と技術交流を推進する取り組みが進められています。
以上のように、モディ政権は2007年以降の動き(シン政権時代の政策)を引き継ぎながら、Make in Indiaを軸とした大規模な国内製造振興策を多角的に進めています。補助金や優遇スキームの導入、海外との連携強化などを通じて、インド国内での半導体生産拡大と自給率向上を目指しているのが大きな特徴といえます。
2.インドが半導体国産化に踏み切った背景
インドが半導体の国産化に踏み切ったのには、概ね次のような理由があると考えられています。
対中貿易赤字の拡大
2010年代半ばから、中国製の格安スマートフォンがインド市場で急速にシェアを伸ばしたことから、それが対中輸入急増の主因となったと考えられています。近年は輸入から国産化へ切り替える動きが進んでいるものの、それは携帯電話の最終組み立て工程であり、半導体を含む付加価値の高い部品は、依然として多くを中国に依存している状況です。貿易赤字の拡大を受けたルピー安、それにともなうインフレによる景気悪化リスクを抑制するには、通信機器向け半導体の国内生産体制を構築する必要があったといえるでしょう。
雇用の創出
半導体産業は、資本・知識集約型の産業であることから、雇用創出効果はどうしても限られる傾向にあります。しかし、パッケージングや検査を含む後工程、PCB(プリント配線基板)への半導体の組み込み工程などでは、一定の雇用創出が期待されています。
貿易構造の変化
インド政府は、半導体の付加価値の約5割を占める「設計」を含め、半導体の国産化を実現することで財輸出における国内付加価値率を引き上げ、IT分野のサービス輸出を拡大することを目指しています。現在海外に流出しているIT高度人材の国内還流が進めば、設計分野でインドが輸出ハブになることも十分考えられるでしょう。
3.インドの半導体国産化が成功するための要素
インドの半導体国産化計画が成功するかどうかは、次の3点におけるビジネス環境の整備の進捗にかかっています。
電力インフラの充実
電圧の一時的な低下や短時間の停電は、半導体生産の障害になる恐れがあります。経済成長は電力需要を引き上げる要因の一つであることから、電力供給の安定性を高めるため、配電公社が電力価格引き上げなどの改革を行い、送配電インフラ整備を整える必要があるものと考えられます。
水資源の確保
半導体を生産する際は、部品洗浄・設備冷却といったプロセスで大量の水を用いることになります。しかし、インドは深刻な水不足に至るリスクを各地で抱えている状況のため、地下水汲み上げの制限や、安定して水を確保するための設備に予算を割り当てるなどの対応が求められます。
人材確保・育成
インドは理工系人材が豊富である一方、半導体産業における即戦力は少ない傾向にあり、トップの大学以外の大学生のレベルが低いことから、インドの半導体産業発展を持続化するためには、教育体制の底上げができるかどうかが重要になります。
4.日本はインドとどう協力し合うべき?
米国や欧州と同様、日本もまたインドとの協力体制構築に心を砕いている状況です。JETROによると、インド大手財閥タタ・グループ傘下のタタ・エレクトロニクスは、半導体製造装置大手の東京エレクトロンとの提携を発表しています。2024年4月には、日印半導体協力の具体化を目的として「JCCII半導体委員会」が発足しており、委員会への参加企業数は80社を超える状況となっています。
新電元工業でも、インド車載市場は今後大きく成長するものと予想しており、インド国内でデバイス開発からユニット開発までを一気通貫で行えるよう、全社一丸となって体制構築を推進します。
5.まとめ
インドは2007年から半導体産業の育成を進めており、2014年からスタートした「Make in India」プログラムは、2024年現在もインドの経済成長・雇用創出・世界的競争力の促進に貢献しています。半導体分野においては、対中貿易赤字の削減、雇用創出、貿易構造の転換などを目的として、半導体の国産化を目指している状況です。半導体国産化の成功のためには、電力インフラの充実や水資源の確保、教育体制の底上げなどがポイントになるでしょう。世界各国がインドとの協力関係構築を模索しており、日本企業もまた、このトレンドに乗れるかどうかが成長の分かれ目となるはずです。